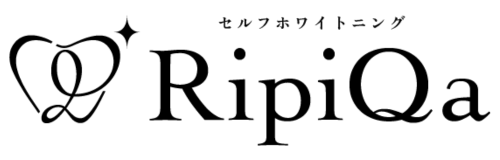歯ぎしり、食いしばりは口腔内の悪習慣の1つとされています。
約10%の方がしているといわれていますが、本人は気づかないことも多く、ご家族に指摘されて初めて気づくというケースもあります。
朝起きた時に頬や首回りが疲れた感じはないですか?
慢性的な疲労感や肩こり、頭痛などの症状が続くという方は、もしかしたら歯ぎしりや食いしばりも原因のひとつかもしれません。
歯ぎしり、食いしばりの原因は明確になっていませんが、ストレスや歯並びの乱れ、咬み合わせ不良などが要因と考えられているので、対策についてご紹介します。
歯ぎしり、食いしばりによる悪影響

歯ぎしりを行うことで、
・歯の咬み合う面がすり減ってしまう
・知覚過敏を進行させる
・顎関節症のリスクを高める
・頭痛や肩こりなどの原因となる
といった悪影響があります。
通常、安静時は上下の歯の間にわずかに隙間があるのが普通ですが、長時間にわたり歯の接触が続くと、顎の筋肉や関節に負担がかかります。
また、就寝時に発生する歯ぎしり、食いしばりはなかなか自覚症状がなく、家族に指摘されて気が付いた、という場合も少なくないです。
日中の歯ぎしり、食いしばりにおいては外部環境や生活習慣に由来する癖といった側面が強いため、自分自身でどんな時に歯を食いしばったり、歯ぎしりをしているかを一度確認し、意識して行わないように習慣を変えていきましょう。
歯ぎしりや食いしばりは、放っておくと口腔内のトラブルはもちろん、さまざまな全身の不調を招く恐れがあります。
「歯ぎしりは放置していても大丈夫」といった認識は危険です。
早めに歯科医院で治療するようにしましょう。
歯が擦り減ってしまう、「咬耗」にも注意!

歯ぎしりによって歯が擦り減り、むし歯や歯周病でもないのに冷たいものがしみたり、咬むと痛みを引き起こすものに、咬耗(こうもう)があります。
咬耗とは歯がすり減ってしまって、硬いエナメル質の下にある、象牙質が露出して刺激を感じてしまう状態になることをいいます。
咬耗自体は、誰にでも起こるものであり、特別珍しいことではありません。
毎日の食事によって少しずつ歯への負担は増加していきますが、過度の咀嚼のほか、硬い食べ物や特殊な嗜好物の常食などの食生活や、就寝時の歯ぎしり、スポーツを行う際の歯の食い縛りなど、悪い口腔習癖や歯への負担となる食生活などにより、さらに歯が削れてしまいます。
咬耗は気づかないうちに日々の積み重ねによってジワジワと歯が削れていくため、歯の形が変化したり、冷たいものなどがしみる「知覚過敏」が症状として出てきます。
予防策としては日常生活においてできるだけ歯への負担をかけないようにしていきましょう。
寝る時の歯ぎしりや食いしばりが強いことにより咬耗が起こっている場合には、歯がすり減るのを防止するため、就寝時にマスウピースを使用する場合があります。
咬耗著しくて歯の機能を損なう場合は、きちんと治療を受けねばなりません。
気になる症状がある時には歯科医院でご相談ください!